釣りを楽しむ場所として、川や湖だけでなく用水路も注目されています。しかし、用水路釣りには「許可」が必要な場合があることをご存じでしょうか。本記事では、用水路での釣りを安全かつ合法的に楽しむために知っておきたい情報をお届けします。
長野県や松本市など、特定の地域では独自のルールが設けられています。エサ釣りやルアーを使った釣り、さらにはヤマメなどの魚を対象とする場合は、漁業権や仕掛けの制限に注意が必要です。また、「魚を取っていい」のか迷う場面や、夜釣りやガサガサ採取に関する法律・マナーについても触れます。
さらに、用水路で釣りをする際の「違法」と密漁との境界線についても解説します。特に、農業用水や灌漑のために整備された用水路では、地元住民や環境への配慮が欠かせません。これらのルールを守ることで、安全で楽しい釣りを実現できるでしょう。
初心者から経験者まで、用水路釣りを最大限に楽しむための情報をまとめています。ぜひ最後まで読んでみてください。
- 用水路釣りに許可が必要な理由や漁業権の存在について理解できる
- 長野県や松本市を含む地域特有の釣りルールや遊漁券の必要性について把握できる
- 夜釣りやガサガサ採取など特定の行動に関連する法律やマナーを学べる
- 違法行為や密漁との境界線と適切な釣りの方法を知ることができる
用水路で釣りをする際の許可は必要?

- 用水路で釣りをする際の許可は必要?
- 用水路での釣り許可が必要な理由とは?
- 釣りは違法?密漁との境界線を知る
- 用水路の管理は誰がしているのか?
- 長野県や松本市での用水路釣りのルール
- ヤマメや他の魚を釣る際の注意点
- 用水路釣りの許可に関する基本情報
用水路での釣り許可が必要な理由とは?
用水路で釣りをするときに許可が必要な場合があるのは、魚を守り、自然環境や地元のルールを尊重するためです。用水路は、農業用や灌漑のために作られた施設ですが、そこに魚が住んでいることも少なくありません。一部の地域では、その水域に漁業権という特別な権利が設定されています。
漁業権とは、そのエリアで魚を管理し保護するために地元の漁業協同組合(漁協)が持つ権利です。この漁業権がある場所で釣りをするには、遊漁券という釣りの許可証を購入する必要があります。遊漁券を買うことで、その地域の魚の保護活動や稚魚の放流といった取り組みに貢献できます。
例えば、ヤマメやアユのような魚が生息している用水路では、遊漁券が必須になることがよくあります。
一方で、ザリガニやブルーギルのような外来種や、漁業権の対象外の魚を釣る場合は、許可がいらないこともあります。ただし、用水路が私有地内にある場合は、釣りをする前に土地所有者の許可を得ることが大切です。
また、用水路の水は地域住民が使っているため、ゴミを捨てたり、農地に無断で立ち入ったりしないように注意しましょう。
地域によってルールが違うため、事前に漁協や自治体に問い合わせて確認することが必要です。ルールを守らないと、罰金を科されたり地元住民とのトラブルに発展することがあります。
適切に確認して釣りを楽しむことで、周りの人々や環境への配慮も忘れずに済みます。
釣りは違法?密漁との境界線を知る
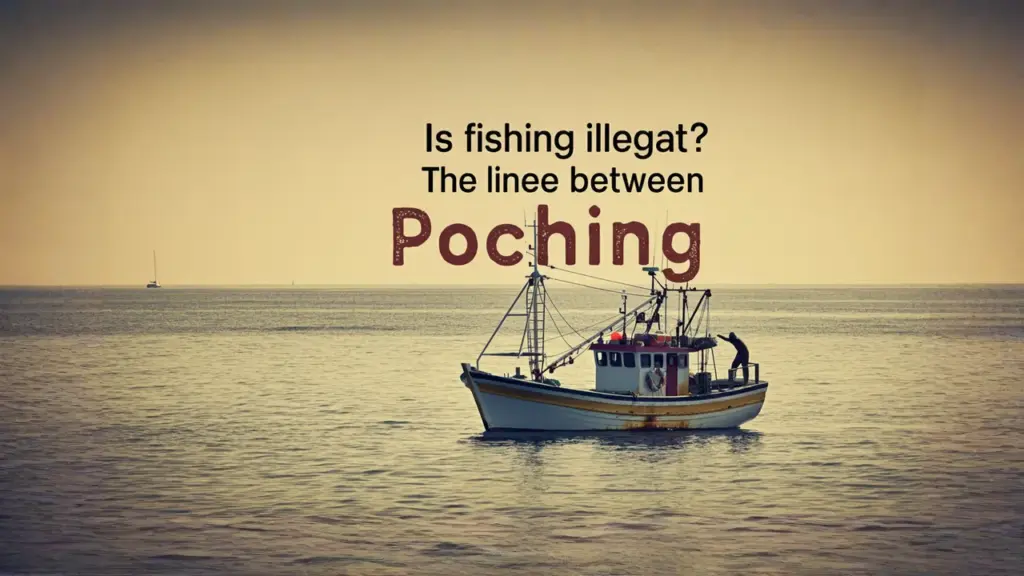
釣りが違法とされるのは、漁業権が設定された場所や禁漁区で、許可を得ずに釣りをする場合です。このような行為は「密漁」と呼ばれ、法律で処罰される可能性があります。
例えば、漁業権があるエリアでは、遊漁券を購入して釣りをする必要があります。これを無視すると違法となり、場合によっては高額な罰金が科されることもあります。
また、禁漁期間中に特定の魚を釣ったり、法律で規制された仕掛けや道具(例:特定の網や電気を使った道具)を使用することも違法行為です。これらは漁業法により厳しく規制されています。
一方、漁業権が設定されていない場所や対象外の魚種を釣る場合は、法律違反にはなりません。ただし、用水路や小川のように漁業権の有無が分かりにくい場所では、注意が必要です。知らないうちに漁業権対象の魚を釣ってしまうと、密漁とみなされる場合があります。
違法な釣りを避けるためには、以下の手順を守ることが重要です。
- 地域のルールを確認する:漁協や自治体に問い合わせて、釣りが許可されているかを調べましょう。
- 遊漁券を購入する:必要な場合は、地元の漁協や釣具店で遊漁券を購入してください。
- 禁漁期間とエリアを把握する:特定の魚が保護される時期や場所では釣りを控えることが大切です。
また、釣りが合法でも、環境や地域住民への配慮を忘れないことが重要です。釣り場にゴミを捨てたり、農地や私有地に無断で立ち入ったりするのは、トラブルの原因になります。
密漁行為は、地域社会との信頼を損なうだけでなく、生態系や自然環境に悪影響を与えることもあります。法律を守りながら釣りを楽しむことで、自然と人のつながりを大切にし、長く釣りを続けられる環境を守りましょう。
用水路の管理は誰がしているのか?
用水路の管理は、地域や目的によって異なりますが、主に以下の3つの主体によって行われています。
- 自治体や地方公共団体 多くの用水路は地域のインフラとして自治体が管理しています。これは、農業用水や灌漑用水を効率的に供給するためです。自治体が直接的に用水路の整備や水量管理を担当することが多く、水質や設備の状態を定期的に確認しています。
- 農業協同組合(JA)や地元農家 農業用水を利用している地域では、農業協同組合や地元の農家が主体となって用水路を管理していることがあります。たとえば、定期的に清掃を行ったり、水の流れを調整したりすることで、農地に必要な水を安定的に供給しています。また、農家や農業団体同士が協力して、用水路を維持する場合もあります。
- 漁業協同組合(漁協) 用水路に漁業権が設定されている場合、その水域の管理や魚種保護は漁業協同組合が担当します。漁協は漁業法に基づいて魚の保護を行い、遊漁券を販売することで、収益を魚の放流や水域の保全活動に充てています。特定の魚が生息する用水路では、漁協が水質や魚の生態系を監視し、適切な管理を行っています。
管理者の確認方法
用水路を利用する際、管理者が誰か分からない場合があります。このようなときは、以下の方法で確認すると良いでしょう。
- 自治体に問い合わせる:市区町村の役場や水道課に問い合わせると、管理者が特定できる場合があります。
- 地元住民や農家に相談する:近隣の農家や地元の方に尋ねると、管理者や利用ルールについて教えてもらえることがあります。
- 漁協に確認する:漁業権が関係している場合は、地元の漁協に直接問い合わせるのが確実です。
管理者に確認せずに釣りを始めると、ルール違反となる可能性があります。また、用水路が私有地内にある場合は、土地所有者の許可も必要です。
長野県や松本市での用水路釣りのルール

長野県や松本市の用水路で釣りを楽しむ際には、地域特有のルールをしっかり守ることが求められます。これらのルールは、用水路の利用目的や漁業権に基づいて設定されています。
漁業権と遊漁券
長野県の多くの用水路や川には漁業権が設定されています。この漁業権がある水域で釣りをする場合、必ず遊漁券を購入しなければなりません。遊漁券は、地元の釣具店や漁協の窓口で購入できます。ヤマメやアユなど、漁業権対象魚種を釣る際には、この遊漁券が必要です。
遊漁券を購入することで、漁協の活動を支援できます。漁協は、稚魚の放流や魚の生態系を守るための活動を行っており、その費用は主に遊漁券の収益で賄われています。
禁止事項
長野県や松本市の用水路では、以下の行為が禁止されていることが多いです。
- 農地への無断立ち入り:用水路は農地と隣接している場合が多く、無許可で田んぼや畑に入ることは迷惑行為とみなされます。
- ゴミの放置:釣り場にゴミを捨てることは絶対に避けましょう。自然環境を守るためにも、ゴミは必ず持ち帰るべきです。
- 夜間の釣り:松本市では、夜間の釣りはトラブルの原因になりやすいとされています。周囲の住民に迷惑がかからないよう、明るいうちに釣りを終えるのが無難です。
ルールの確認方法
用水路釣りをする前には、以下の方法でルールを確認しておきましょう。
- 漁協や自治体に問い合わせる:漁業権の有無や必要な遊漁券について正確な情報を得ることができます。
- 地元の釣具店で聞く:遊漁券の購入と同時に、その地域特有のルールについて詳しく教えてもらえます。
- 現地で注意書きを確認する:釣り場近くにルールが記載された看板が設置されている場合があります。これを確認してから釣りを始めましょう。
地域に配慮した行動
長野県や松本市の用水路で釣りを楽しむ際は、環境と地域住民に配慮することが大切です。例えば、釣りをする際に農地を荒らしたり、水域を汚したりすると、地域住民との関係が悪化する可能性があります。
ルールを守り、適切な場所と方法で釣りを行うことで、地域社会や自然環境への負担を減らしながら、安全で楽しい釣り体験を実現できます。
ヤマメや他の魚を釣る際の注意点

ヤマメなどの魚を釣る場合は、漁業権や禁漁期間、仕掛けのルールなど、守るべき注意点がいくつかあります。これらを理解し守ることで、トラブルを避けながら釣りを楽しむことができます。
1. 漁業権と遊漁券の確認
ヤマメは多くの地域で漁業権が設定されている魚種です。そのため、釣りをする際には遊漁券の購入が必須です。遊漁券は、地元の釣具店や漁業協同組合(漁協)で購入できます。購入する前に、どのエリアで有効なのか、対象魚種が何なのかを確認しておくと安心です。
2. 禁漁期間に注意
ヤマメには繁殖期を守るための禁漁期間が設定されている地域が多くあります。この期間中に釣りをすると違法行為とみなされるため、事前に地域の漁協や自治体に確認してください。通常、禁漁期間は秋から冬にかけて設定されることが多いです。
3. 使用する仕掛けや道具
釣りに使う仕掛けにもルールがある場合があります。特に、ヤマメを釣る際には、指定された釣り方や道具を守ることが求められます。例えば、禁止されている地域でのトリプルフックやルアーの使用は違法となる可能性があります。必ず現地のルールを確認してから釣りを始めましょう。
4. キャッチアンドリリースのルール
ヤマメのような希少性の高い魚を保護するため、一部の地域ではキャッチアンドリリースが推奨または義務付けられていることがあります。釣った魚を傷つけないよう、バーブレスフック(返しのない針)を使う、素早く魚を水に戻すなど、釣り方にも配慮が必要です。
5. 周囲の環境を守る行動
釣り場では環境保護が重要です。ゴミを捨てず持ち帰ることはもちろん、岸辺の植物を踏み荒らしたり、水質を汚したりしないように注意してください。また、ヤマメが生息する川や用水路では、水の透明度や流れが重要な要素となるため、釣り以外の活動でも環境への影響を考慮する必要があります。
6. 地域の住民や他の釣り人への配慮
釣り場が地元住民や他の釣り人にとっても共用スペースであることを忘れず、迷惑をかけないよう心がけましょう。特に、農地や私有地に無断で立ち入ることは避け、周囲の人々との調和を保ちながら釣りを楽しむことが大切です。
ヤマメを含む魚を釣る際には、これらの注意点を守ることで、トラブルを防ぎ、自然環境を尊重した釣りを楽しむことができます。ルールを守りながら、安全で充実した釣りの時間を過ごしましょう。
用水路釣りの許可に関する基本情報

- 仕掛けやルアー釣りで注意すべき点
- ガサガサ採取は許可が必要なのか?
- 夜間の釣りで守るべきルール
- エサ釣りで知っておくべき法律
- 魚を取っていい範囲を理解する
- 川での釣りと用水路釣りの違い
- 用水路釣りを楽しむためのマナーと配慮
仕掛けやルアー釣りで注意すべき点
仕掛けやルアー釣りは、釣りの種類や地域ごとに守るべきルールや注意点が異なります。それらを理解して行動することで、より安全でトラブルのない釣りを楽しむことができます。
1. 仕掛けの選択はルールに従う
地域によっては、使用できる仕掛けに制限が設けられている場合があります。例えば、トリプルフック(3本針)や特定のサイズのフックは、一部の水域で禁止されています。また、返しのついた針を使用するとキャッチアンドリリースが困難になり、魚に大きなダメージを与える可能性があります。そのため、バーブレスフックを選ぶことをおすすめします。
2. ルアーの使用に関する規制
ルアー釣りは、魚を効率的に狙える一方で、誤って漁業権対象の魚を釣ってしまうリスクがあります。漁業権が設定されている水域では、ルアーの使用自体が制限されている場合もあるため、事前に漁協や地元のルールを確認してください。
3. ターゲットの魚種を明確にする
仕掛けやルアーを選ぶ際には、ターゲットの魚種を意識することが重要です。例えば、ブラックバスやブルーギルを狙う場合、漁業権が関係ないことが多いですが、アユやヤマメなどを狙う場合は必ず遊漁券が必要です。誤って規制対象魚を釣らないよう、仕掛けやルアーの選択に注意しましょう。
4. 環境に配慮した仕掛けの使用
仕掛けが水中の障害物に絡まった場合、引っ張り続けてラインを切ると、仕掛けがそのまま水中に残り環境汚染の原因になります。ルアーや仕掛けを回収できるような方法を取るか、環境負荷を最小限にする素材を選ぶことが大切です。
5. 他の釣り人とのマナーを守る
仕掛けやルアー釣りはキャスト(投げる動作)が必要なため、周囲の人との距離が近いと事故につながる恐れがあります。広い場所を選び、他の釣り人と適切な距離を保つことが重要です。また、大きなルアーを使う場合は特に慎重に行動しましょう。
ガサガサ採取は許可が必要なのか?

ガサガサ採取とは、網などを使って水辺で小魚や水生生物を捕まえる方法で、子どもから大人まで気軽に楽しめる活動です。しかし、許可が必要かどうかは場所や対象生物によって異なります。
1. 漁業権の有無を確認する
漁業権が設定されている水域では、ガサガサ採取も制限される場合があります。漁業権対象の魚(例えばアユやヤマメなど)を捕まえると、たとえ少量であっても違法行為とみなされることがあります。そのため、ガサガサ採取を行う前に、地元の漁協や自治体に問い合わせて確認することが重要です。
2. 対象生物による許可の違い
ザリガニやヌマエビ、ヨシノボリなど、漁業権の対象外の生物を採取する場合は、許可が不要なことがほとんどです。ただし、特定外来生物(例えばアメリカザリガニ)を持ち帰る場合は、生物多様性に関する法律に基づき注意が必要です。禁止されている場所での採取や不適切な持ち帰りは問題となることがあります。
3. 私有地内での採取
ガサガサ採取をする水域が私有地にある場合、土地所有者の許可が必要です。無断で立ち入ると不法侵入にあたる可能性があるため、必ず事前に確認してください。
4. 環境保全の意識を持つ
ガサガサ採取は環境に配慮して行う必要があります。例えば、岸辺の植生を荒らしたり、水生生物の生息地を壊したりしないように注意してください。また、採取した生物を不用意に別の水域へ移動させると、生態系に悪影響を与える場合があります。
5. トラブルを避けるための事前確認
ガサガサ採取をする前に、以下のことを確認しましょう:
- 地域のルールや禁止事項を把握する。
- 採取する生物の種類とその扱いについて理解する。
- 必要に応じて漁協や自治体に問い合わせる。
ガサガサ採取は手軽な楽しみですが、ルールを守らないとトラブルや違法行為につながる可能性があります。適切な方法で行い、自然を大切にしながら楽しみましょう。
夜間の釣りで守るべきルール
夜間の釣りは昼間と異なる楽しさがある一方で、特有のリスクやルールを理解しておくことが大切です。暗い環境で釣りを行う際には、安全面だけでなく、地域や法律による規制も守る必要があります。
1. 地域のルールを確認する
多くの地域では、夜間の釣りが制限されている場合があります。特に、河川や用水路が住宅街に近い場合、騒音やトラブルを避けるために夜間の釣りを禁止していることがあります。釣りを計画する前に、地元自治体や漁協のルールを確認しましょう。
2. 必要な装備を準備する
夜間は視界が悪くなるため、適切な装備が必要です。ヘッドランプや懐中電灯は必須アイテムで、安全な移動や仕掛けの操作に役立ちます。また、反射材がついた服を着用することで、他の人や車両から視認しやすくなり、事故を防ぐことができます。
3. 騒音や光に注意する
夜間は音が響きやすく、光が周囲に迷惑をかけることがあります。仲間と会話する際や道具を扱うときは音量を抑え、周辺住民に迷惑をかけないよう注意しましょう。また、光の使い方も工夫し、周囲を照らしすぎないようにすることが大切です。
4. 漁業権や禁漁区の確認
夜間でも漁業権が設定されている水域での釣りには遊漁券が必要です。また、禁漁区での釣りは時間帯にかかわらず違法行為となります。事前に釣り場の規制を把握しておくことが重要です。
5. 緊急時の備えを忘れない
暗い環境では、事故やトラブルのリスクが高まります。事前に家族や友人に釣り場と帰宅予定時間を伝えておき、携帯電話を常に携行してください。万が一の際に迅速に助けを求めるため、近隣の緊急連絡先も把握しておくと安心です。
夜間の釣りを楽しむには、安全対策とルールの遵守が欠かせません。自然や周囲に配慮しながら、快適な釣りの時間を過ごしましょう。
エサ釣りで知っておくべき法律

エサ釣りは手軽で人気の高い釣りスタイルですが、法律や地域ルールを守ることが重要です。エサ釣りに関わる規制を知り、違反行為を防ぐことで、安全で楽しい釣りが実現します。
1. 漁業権の範囲を理解する
漁業権が設定された水域では、エサ釣りを行う場合でも遊漁券が必要です。これは、漁協がその水域の漁業資源を保護・管理するために設けられたルールです。特に、アユやヤマメなどの漁業権対象魚種を釣る際には、必ず遊漁券を購入してください。
2. 禁漁期間と対象魚種
エサ釣りでは、仕掛けにかかる魚がターゲット以外の種類になることもあります。禁漁期間中の魚種や保護されている魚種を誤って釣った場合でも、リリースせずに持ち帰ると法律違反となる可能性があります。禁漁期間や対象魚種を事前に確認し、必要に応じてリリースを徹底しましょう。
3. 禁止されているエサの種類
一部の地域では、エサの種類に制限がある場合があります。たとえば、動物性エサ(ミミズやアカムシなど)を禁止している場所や、外来種のエサ(特定の貝や甲殻類)を使うことが規制されているケースがあります。現地のルールを守ったエサ選びを心がけましょう。
4. エサの放置や廃棄は禁止
釣り場で使用しなかったエサをそのまま捨てることは環境破壊の原因になります。特に、生き餌は生態系に悪影響を与えることがあり、法律で禁止されている場合もあります。余ったエサは必ず持ち帰り、適切に処理してください。
5. 私有地や管理エリアでの釣り
私有地や管理されているエリアでエサ釣りをする場合、土地所有者や管理者の許可が必要です。無断で立ち入ると不法侵入とみなされ、トラブルになることがあります。許可を取ることで、安心して釣りを楽しむことができます。
エサ釣りは多くの人に親しまれる釣り方ですが、法律やルールを守ることで、安全に楽しむことができます。事前に規制を確認し、環境や周囲に配慮した行動を心がけましょう。
魚を取っていい範囲を理解する
魚を取る際には、法律や地域のルールを守ることが最も重要です。魚を取ってよい範囲は、漁業権や環境保護の観点から明確に定められている場合が多いため、それを事前に確認しておくことが必要です。
1. 公共の水域と私有地の違い
公共の川や湖であっても、多くの水域には漁業権が設定されています。この場合、遊漁券を購入していないと魚を取ることはできません。一方で、私有地内の池や用水路では、土地の所有者の許可が必要です。無断で立ち入ると不法侵入となる可能性があるため注意しましょう。
2. 漁業権の対象魚種
漁業権が設定されている場所では、対象魚種が具体的に指定されています。例えば、アユ、ヤマメ、サクラマスなどがこれに該当します。これらの魚を取る場合、漁業協同組合が発行する遊漁券を購入する必要があります。一方、ザリガニやブルーギルといった外来種は、漁業権の対象外とされていることが多く、許可なしで取れる場合があります。
3. 禁漁区と保護区域
特定の魚種を保護するために禁漁区や禁漁期間が設定されている場合があります。これらの区域や期間中に魚を取ることは法律で禁じられています。また、自然保護区などでは魚を取ること自体が全面的に禁止されている場合もあります。
4. 釣り以外の採取活動
釣り以外の方法で魚を取る場合も、法律の規制があります。例えば、網や罠を使った方法には特別な許可が必要な場合があります。地域によっては、これらの道具の使用が全面的に禁止されていることもあります。
5. 地域のルールを確認する方法
魚を取ってよい範囲を正確に把握するには、地元の漁協や自治体に問い合わせるのが最も確実です。また、釣り場や水辺には規制内容を示す看板が設置されていることが多いので、それを確認することも大切です。
魚を取る行為は楽しみの一環ですが、ルールを守らないと違法行為となる場合があります。適切な情報を事前に収集し、安全でトラブルのない時間を過ごしましょう。
川での釣りと用水路釣りの違い

川での釣りと用水路での釣りには、環境やルール、釣れる魚種など多くの違いがあります。これらを理解することで、場所に応じた適切な準備と行動が可能になります。
1. 環境の違い
川は自然環境の一部であり、水深や流れの強さが場所ごとに異なります。一方、用水路は主に農業用や灌漑目的で作られた人工的な水路です。そのため、川は多様な生態系を持つのに対し、用水路は管理された環境で魚が生息しています。
2. 漁業権の違い
川には漁業権が設定されていることが多く、釣りをする際には遊漁券が必要です。特にアユやヤマメといった漁業権対象魚種を釣る場合、遊漁券の購入が義務付けられています。一方、用水路では漁業権が設定されていない場合もありますが、魚種やエリアによって異なるため、事前に確認が必要です。
3. 釣れる魚種
川ではアユ、ヤマメ、イワナ、ウグイなど多種多様な魚が釣れることが一般的です。一方、用水路ではコイ、フナ、ブルーギル、ザリガニなど、比較的小型の魚や外来種が多く見られます。川釣りでは多様性を楽しむことができ、用水路では手軽さが魅力です。
4. ルールとマナーの違い
川釣りでは、漁協が設定したルールや禁漁区を守ることが求められます。また、自然環境を保護するため、釣り場でのゴミの持ち帰りや植物を荒らさないといった基本的なマナーが重要です。一方、用水路釣りでは農地や私有地に隣接することが多いため、土地所有者への配慮が特に必要です。
5. 釣り方の違い
川釣りでは流れに対応するための仕掛けやタックルが必要で、キャスティングや流れを読む技術が求められることがあります。一方、用水路釣りは浅瀬や狭い範囲で行うことが多いため、簡易的な道具や短い竿が適しています。
川と用水路では、釣りの魅力やルールが異なります。それぞれの特性を理解し、適切な装備とマナーを心がけることで、どちらの釣りも十分に楽しむことができます。
用水路釣りを楽しむためのマナーと配慮

用水路釣りは手軽に楽しめる反面、地域住民や自然環境への配慮が欠かせません。マナーを守ることで、トラブルを避けながら釣りを楽しむことができます。以下では、具体的なマナーと配慮すべきポイントについて説明します。
1. 釣り場の許可を得る
用水路は多くの場合、農業や地域の生活に密接に関わっています。そのため、釣りをする際には、その場所が公共の水路か、私有地や農地内にあるかを確認しましょう。私有地や管理区域の場合は、必ず土地所有者や管理者の許可を取ることが大切です。
2. ゴミは必ず持ち帰る
釣り場にゴミを残す行為は、環境汚染だけでなく、地元住民とのトラブルの原因にもなります。使い終わった釣り糸やエサのパッケージ、飲み物の空き容器などは、必ず持ち帰りましょう。ゴミを捨てないことは釣り人としての基本的なマナーです。
3. 農地や水路周辺を荒らさない
用水路は農地と隣接していることが多く、農家の方々が大切に管理しています。釣りをする際には、農地や用水路の構造物を壊さないよう注意してください。また、無断で農地に立ち入る行為は、迷惑行為となるだけでなく、法的なトラブルに発展する可能性があります。
4. 騒音を控える
用水路は住宅地に近い場所や静かな田園地帯にあることが多いため、釣りを楽しむ際には騒音を出さないよう気をつけましょう。大声での会話や音楽を流す行為は周囲に迷惑をかける可能性があります。静かに釣りを楽しむことで、周囲の人々にも配慮しましょう。
5. 地域ルールを確認する
用水路によっては、釣りが禁止されている場所や、特定の魚種を釣る際に許可が必要な場所があります。地元の漁協や自治体の規則を事前に確認し、違法行為を避けるようにしましょう。漁業権がある場合は遊漁券を購入するのも忘れないようにしてください。
6. 環境への影響を最小限に抑える
用水路の自然環境は、小魚や水生植物などの生態系を支えています。仕掛けが引っかかった場合は無理に引っ張らずに回収し、余ったエサを水中に放置しないようにしましょう。また、採取した魚を別の場所に放流する行為は生態系を乱す可能性があるため控えてください。
7. 他の利用者との共存
用水路は釣り人だけでなく、農家や散歩を楽しむ人々、近隣住民など多くの人々に利用されています。他の利用者の邪魔にならないよう、釣り具を広げすぎたり、水路を独占する行為を避けましょう。譲り合いの精神を持つことが大切です。
8. 夜間釣りへの注意
夜間に釣りを行う場合、光や音が近隣住民に迷惑をかけることがあります。ヘッドランプなどの光量を調整し、静かに行動するよう心がけましょう。また、夜間の釣りが禁止されている地域もあるため、事前に確認してください。
用水路釣りを楽しむには、環境や地域住民への配慮が欠かせません。マナーを守ることで、地域社会との良好な関係を築きながら、安心して釣りを楽しむことができます。釣り場を後にする際は、来たときよりも美しい状態にすることを心がけましょう。
用水路釣りでの許可の基本と守るべきポイント
記事のポイントをまとめますね!



