梅雨の釣りは、6月に愛知や千葉、関東で釣行を計画する人にとって重要なシーズンです。
雨の日に釣れにくい理由を理解し、適切なコツを押さえることで釣果アップを狙いやすくなります。本記事では、夜釣りルアーの選び方、泳がせ釣りやフカセ釣りの方法、船釣りや堤防で狙える魚種、青物やチヌ、バスなどの攻略ポイントを体系的に整理します。
さらに、梅雨時期のタイドグラフの活用法、釣行準備やファッションの基本、ルアーカラーの選択基準まで幅広く解説します。加えて、潮汐や気圧変動が魚の行動に与える影響、地域ごとの釣果傾向、安全装備やウェアリングの基礎なども、初心者が理解しやすいよう専門用語を補足しながら紹介します。
堤防や船、河川や汽水域といったフィールド別の特徴にも触れ、現場で迷わず実践できる判断基準と手順を身につけられるよう整理しました。
- 梅雨時期の安全対策と気象・潮汐の実践活用
- 6月に強いルアー選びとカラー戦略
- 堤防・船・磯・河川別の魚種と攻略
- 地域傾向と次アクションまでの具体手順
梅雨の釣りで知っておきたい基本と安全

- 釣行準備のチェックリスト
- 梅雨時期のタイドグラフ活用法
- 雨の日に釣れない理由と釣果アップのコツ
- 6月の夜釣りルアー攻略法
- 梅雨時期に有効なルアーカラー選び
- 梅雨の釣行に最適なファッション
釣行準備のチェックリスト

梅雨時期は安全と情報の質が釣果を左右します。
現場の意思決定を早く、正確にするためには、天候・潮汐・装備・撤収条件を事前に言語化し、チェックリスト化しておくことが有効だと示されています。ここでは、気象(降雨・風・雷)、水位・潮位、装備、連絡・退避の四領域に分け、各項目の確認ポイントと専門用語の意味を整理します。
なお、降雨量(mm/h)や風速(m/s)、潮位(cm)は単位の違いで体感がずれやすいため、数値と現場感覚を紐づけて覚えることが推奨されます。
| 項目 | 確認ポイント | 参考/根拠 |
|---|---|---|
| 気象警報・雷 | 警報・注意報の種別、雷活動度、積乱雲の発達 | 公的な防災情報で最新状況を確認する方法が案内されています |
| 風向・風速 | 平均風速と最大瞬間風速、岸向き/沖向きの風 | 瞬間風速が平均の1.5〜2倍程度まで上がる傾向があると説明されています |
| 潮汐・潮位 | 干満時刻、潮位差、狙いの時間帯の潮流変化 | 潮位表は地点ごとに干満と潮位を推算・表示する仕組みが示されています |
| 増水・濁り | 河川水位の上昇トレンド、放流情報の有無 | 河川の監視網で水位変化を客観的に把握できるとされています |
| 装備 | PFD(桜マーク)/防水透湿/予備ライト/替えフック | 救命胴衣の常時着用が推奨され、型式承認の指標が公開されています |
| 連絡・退避 | 行程共有、撤収基準(数値化)、避難先の事前確認 | 海や河川の安全に関する周知資料で基本が解説されています |
専門用語の補足として、平均風速(一定時間に観測した風速の平均)と最大瞬間風速(瞬間的に観測された最大値)は異なる概念です。キャストやラインメンディングに影響するのは突風であることが多く、瞬間風速が10m/sを超えると軽量ルアーの飛行姿勢が乱れやすいという傾向があります。
また、潮位差(満潮と干潮の差)が大きい日は港内でも流速が上がりやすく、係留船やケーソンの周りにヨレ(流れの乱れ)が発生してベイトが溜まりやすいと解釈されます。
河川合流点や雨水吐け口では濁りの境界(カレントライン)が視認できることがあり、こうした線状の変化は狙いどころになりやすいと一般に言われます。
最新の警報・注意報、雷の短時間予測、土砂災害警戒情報などは公的機関の公開情報を確認できます(出典:気象庁 防災情報)。
おすすめアイテム
釣行中の濡れた足場や波被りによる落水リスクに備えるなら、このJ-FISHネオベストJNV-441がおすすめです。ネオプレン素材でソフトな着用感ながら、米国コーストガード認定&小型特殊船舶検査対応の高い安全性能。
フロントジッパーとバックルで確実にフィットし、Dリングやホイッスル付きで緊急時の装備としても充実。撥水ジャージで蒸れにくく快適な安全ライフを支えます。
梅雨時期のタイドグラフ活用法
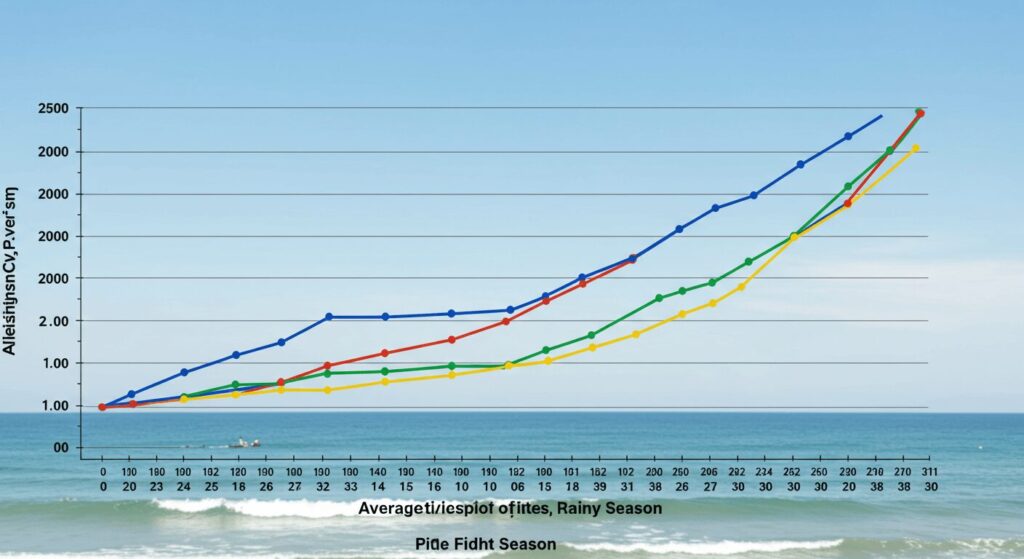
梅雨は降雨による塩分濃度や水温の変化が大きく、潮汐サイクルと重なると魚の接岸タイミングや摂餌レンジがずれやすい時期です。
タイドグラフ(潮位の時間変化を示す図表)を使う目的は、
- 潮位差の大きい時間帯を把握する
- 干満の前後2〜3時間に集中する
- 地形と水路の関係を重ねて読む
という三点に集約されます。
潮位差が大きければ一般に流速も高まり、堤防の角やスリット、橋脚の下流側に反転流(逆向きの小さな流れ)が生じ、ベイトが停滞しやすいと考えられます。
逆に潮位差が小さい日や小潮では、ストラクチャー(障害物)にタイトに付く個体を一つずつ拾う展開が適しています。
読み方の要点
グラフ上で注目すべきは、干潮・満潮の時刻と潮位曲線の傾き(傾きが急=水位の変化が速い)。
港内なら満潮前後で岸際に当たるカレントに沿って回遊する小型青物、河口なら下げ始めに濁り線が形成されバスやシーバスの摂餌スイッチが入りやすい、というように、時刻・場所・魚種をセットで予測します。
さらに、水温(℃)が日中の短時間で1〜2℃上下するだけでも表層の活性が落ちる場合があり、曇雨天で日射が弱い日はレンジを下げた釣り(中層〜ボトムのスロー展開)へ素早く移行する準備が役立ちます。
| 条件 | 狙い方の目安 |
|---|---|
| 潮位差大 | 潮目・反転流に通し回遊待ち。回収前に一拍ストップで食わせ |
| 潮位差小 | 敷石や桟橋脚のピンを丁寧に。スロー〜デッドスローで見せる |
| 干潮前後 | シャロー退避のベイトを表層系で拾い、時合い短期決戦 |
| 満潮前後 | 岸際のカレント横切りコースでリアクションバイトを誘う |
専門用語の補足:カレントは潮汐・風・地形で生じる水の流れ、ヨレは流れの境界で渦や停滞が起きる帯、反転流は主流と逆向きの局所流です。
いずれもベイトが滞留しやすく、魚が定位(特定の位置に留まること)しやすいとされます。こうした場所をルアーが横切る角度を数パターン試し、「角度×レンジ×スピード」の組み合わせを素早く最適化するのが梅雨の効率化に直結します。
なお、複数の流れが交差する堤防角では波被りの危険が増すため、足場の高さや退避経路をあらかじめ確認しておくと安全度が高まります。
雨の日に釣れない理由と釣果アップのコツ

降雨は水色(透明度)・光量・溶存酸素・水温・流速を同時に変化させ、魚の摂餌レンジや回遊コースを短時間で移動させます。とくに梅雨の強雨直後は、濁りの急変と水温の短期低下、気圧低下が重なり、普段の実績コースに魚が通らない「空振り時間」が発生しがちです。
これを回避するには、
- 視認・検知されやすい要素を増やす
- 濁り境界とヨレを優先する
- 一時的なレンジ低下に合わせる
この三つを軸に、ルアーの波動・サイズ・レンジ・スピードを組み替えます。
対策のポイント
- 対策視認・検知性の確保
- ポイント
濁りが強いほど、シルエットが太く輪郭が立つカラーと強い波動の組み合わせが有効だと説明されています。塩水域では強波動ミノーやシンキングペンシル、バイブレーション、小型青物にはメタルジグのスロー寄り操作が候補。
淡水や汽水のバスはスピナーベイトやチャターベイトでブレードのフラッシングと波動を活かし、ピンスポットではサスペンドミノーのポーズ(停止)で食わせの間を作るやり方が知られています。
- 対策濁り境界とヨレ
- ポイント
雨水流入でできたカレントラインは、ベイトが流され一時的に溜まるため、等深線や護岸の段差、係留船の風下など、流れの当たる面から順にチェックします。
上下潮(潮位の上げ下げ)と降雨流入が重なる時間帯は回遊サイクルが短く、同一スポットを数分〜十数分のインターバルで打ち直すリズムが奏功する場合があります。
- 対策レンジの適応
- ポイント
冷たい雨で表層水温が下がると、活性の高い個体でもレンジが中層〜ボトムに落ちる傾向があります。
シーバスならシンペンのドリフトからレンジを落としてバイブのリフト&フォール、チヌはボトム系ルアーのスローリトリーブやズル引きへ移行。バスはスイムジグやテキサス、重めジグヘッド+シャッドテールで等速スローを意識します。
- 対策実践のコツ
- ポイント
「増水=岸寄り」という固定観念を避け、風向と流入の合成流、濁り境界、ストラクチャーの風下側を優先。ルアーはサイズ→波動→レンジ→カラーの順で変えると、要因切り分けがしやすいとされています。
- 対策安全配慮
- ポイント
雷鳴の聴取、積乱雲の急発達、強風突風の兆候が見られた場合は退避が推奨されています。公的な短時間予測で雷活動の高まりが示された際は屋外活動を控えるよう周知されています。
- 対策専門用語の補足
- ポイント
ドリフトは流れに同調させてルアーを自然に流す技術、リフト&フォールは持ち上げてから沈める縦の誘い、等速スローは速度変動の少ないゆっくり巻きです。
いずれも視界が悪いときの検知性や食わせの間を意識した操作で、雨天・濁りでの有効性が広く言及されています。
6月の夜釣りルアー攻略法

6月の夜釣りは、昼間のプレッシャーが軽減されるため魚が警戒心を弱めやすく、特に常夜灯周りや河口域など光量差が生まれるポイントで効果が期待されます。この時期の夜釣りでは、潮位変動と光の強弱が重なり合う場所をいかに攻めるかが重要です。
常夜灯下に集まる小魚(ベイト)にシーバスやチヌ、バスなどが着くことが多く、ルアーを流れの当たる側から自然に送り込むようなアプローチが推奨されています。
都市部の港湾では特に、街灯の光と暗がりの境界がはっきりと出るため、ルアーをそこに通すだけでバイトが誘発されやすいと解釈されています。
ルアー選択と操作の工夫
夜間は魚の視覚に頼る度合いが低下し、波動やシルエットでの認知が高まる傾向があります。
表層では細身ミノーやペンシルベイトを使い、ドリフト操作(流れに乗せて自然に漂わせる方法)でベイトの挙動を模倣します。
中層以深では、スローリトリーブ可能なバイブレーションやシンキングペンシルが有効で、潮下に流し込みながら一定速度を保つことで検知されやすくなります。夜風によるラインの膨らみは感度低下の原因となるため、ロッドポジションを下げてテンションを維持するなどの工夫が欠かせません。
また、ルアーカラーは昼間に比べて大きな影響を受けにくいですが、暗色系(黒、ネイビー)はシルエットが強調されやすく、光源の有無に関わらずバイトに結びつきやすい場面があります。明暗部の境界を狙うときにはフラッシング系(シルバーやホロ)の効果も高いとされています。
梅雨時期に有効なルアーカラー選び

梅雨は曇天や雨天による光量不足と、濁流による透明度の変動が顕著な季節です。このため、ルアーカラーの選択が釣果に直結しやすく、特に初心者と上級者の差が出やすい要素とされています。
選び方の基本は「水色(透明度)×光量(日照や月光)×ベイトの種類」の組み合わせです。濁りが強ければ視認性を重視、クリアな水質ではナチュラルカラーを優先します。
例えば、曇天や雨天で濁りが強い状況ではブラックやチャート、オレンジなどのコントラストカラーが効果的です。曇天で濁りが薄い場合はゴールドやピンクなどフラッシング効果のある色が有効です。晴天時やクリアウォーターでは、ベイトに似せたナチュラルカラー(イワシ、キス、アユ系)が違和感を与えにくいとされています。
| 状況 | 推奨カラー例 | 意図 |
|---|---|---|
| 強濁り・曇天 | ブラック、チャート、オレンジ | シルエット強調と強コントラスト |
| 薄濁り・朝夕 | ゴールド、ピンク、パール | フラッシングで光を拡散させる |
| クリア・日中 | ナチュラル、クリア、ベイト系 | 環境に溶け込み違和感を抑える |
ちなみにフラッシングとはルアーの反射光によって魚に存在を知らせる効果で、曇天や濁りで光量が不足する場面で特に有効とされます。またチャートカラーは黄色〜緑がかった蛍光色を指し、強い視認性が特徴です。
メーカー公式サイトでは、レインウェアの撥水性能の低下が釣行時の快適性だけでなく、視認性にも影響すると案内されています。撥水加工が失われると雨粒の付着でルアーの色が見えにくくなることがあるため、定期的なメンテナンスが推奨されています(出典:SHIMANO 公式メンテナンス)。
梅雨の釣行に最適なファッション

梅雨の釣行で最も重要なのは、防水透湿性・速乾性・安全性の3要素です。
雨に濡れたまま長時間活動すると体温低下や疲労蓄積を招き、集中力を欠いた行動が事故に直結することもあります。快適かつ安全に釣行を続けるための服装戦略は、ベース・ミドル・アウターの3レイヤーに分けて考えると整理しやすいです。
- ベースレイヤー
- 速乾性に優れた化学繊維のTシャツやインナーが基本で、綿素材は濡れると乾きにくいため避けるのが望ましいとされています。
- ミドルレイヤー
- 薄手のフリースやインサレーションウェアを選び、保温性と通気性をバランスさせます。
- アウター
- シームテープ加工が施されたレインウェアを選び、透湿防水性(蒸れを逃がしつつ雨を防ぐ性能)を確保することが重要です。
- 足元
- 防滑性能を備えたウェーディングシューズやブーツを選択し、常時ライフジャケットを着用することが推奨されます。さらに、帽子やグローブも雨具と合わせて用意することで体温保持やケガ防止につながります。
環境省の公式情報では、湿度が高い梅雨時期でも熱中症リスクが存在するとされ、風通しの良い服装とこまめな水分補給の重要性が指摘されています(出典:環境省 熱中症予防情報サイト)。
防水透湿ウェアの撥水性能は、定期的な洗濯と専用撥水剤による処理で回復可能とされています。メーカー公式では、洗濯→撥水剤塗布→熱処理(乾燥機やアイロン)が有効と案内されています(出典:SHIMANO 公式メンテナンス)。
おすすめアイテム
梅雨時期の長時間釣りで気になるのが“雨と蒸れ”。このKiUの3レイヤーフィッシングジャケットは、防水透湿性に優れた3層生地で、雨を防ぎつつ湿気を逃して快適さを保ちます。
Dカン付きで小物の取り付けにも便利。リフレクタープリントの収納袋付きなので、夜釣りや朝夕の視認性も考慮されています。普段使いも考慮したデザインで、機能性と見た目の両立にもおすすめです。
梅雨の釣りで狙える魚と地域情報

- 6月堤防で釣れる魚種|青物・チヌ・バス
- 6月船釣りで狙える代表魚
- 6月の泳がせ釣りとフカセ釣りの釣り方
- 6月の愛知・千葉・関東の釣り傾向
- 梅雨釣りの総まとめと次の一手
6月堤防で釣れる魚種|青物・チヌ・バス

6月の堤防は一年の中でも魚種が豊富に狙える季節です。
特に梅雨入り前後は小型青物(ワカシやイナダの若魚)、アジ、サバ、イワシといった回遊魚が接岸する一方、根魚(メバルやカサゴ)、チヌ、シーバスなどの居着き系も活発に行動するため、多様な釣り方に挑戦できます。
サーフに隣接する堤防ではキスやヒラメ、マゴチなどのフラットフィッシュが狙え、汽水域に近い港湾ではブラックバスやシーバスが混じるケースも見られます。
これらの魚は潮汐・天候・時間帯によって接岸や回遊の傾向が変化するため、タイドグラフと気象情報を組み合わせた釣行計画が有効です。
例えば、小型青物は早朝の満潮前後に群れで接岸することが多く、メタルジグやジグサビキで効率的に探れます。チヌは濁りが入った雨後に岸壁際やストラクチャーに寄りやすく、トップウォータープラグでの釣果も報告されています。
バスは流入河川の濁り境界に定位する傾向があり、ソフトルアーやスピナーベイトで攻略する方法が有効です。
| フィールド | 主な魚種 | 有効な仕掛け/ルアー |
|---|---|---|
| 外海に面した堤防 | 青物、サバ、アジ | メタルジグ、ジグサビキ、シンキングペンシル |
| 湾奥・港内 | シーバス、チヌ、メバル | ミノー、バイブレーション、トッププラグ |
| サーフ隣接 | ヒラメ、マゴチ、キス | シンペン、ワーム+ジグヘッド、投げ仕掛け |
6月の船釣りで狙える代表魚

6月の船釣りは対象魚が多く、イサキ、タチウオ、アジ、シロギス、マルイカなどが代表的です。
外洋系ではイサキが群れで狙えるほか、内湾ではシロギスやアジの数釣りが楽しめる傾向にあります。水深と潮流に応じて、仕掛けやタナ取りの工夫が求められます。
イサキは中層に群れるため、ビシ仕掛けでのコマセ釣りが一般的です。タチウオは水深30〜80m付近で群れることが多く、テンヤやジグを使って縦方向に探るのが効果的です。アジはビシアジ仕掛けで数を伸ばしやすく、サビキ仕掛けでも初心者が楽しめます。マルイカはスッテ仕掛けを用い、細やかなアタリを拾うテクニカルな釣り方が人気です。
装備と安全の基本
使用するタックルは軽量ロッド+感度重視のリールが基本で、PE0.6〜1.5号前後、リーダー2〜6号程度が目安とされます。魚種ごとに仕掛けの号数やハリスの長さを調整することで釣果が安定します。
出港前には風速・波高の確認が不可欠であり、海況が不安定な場合は中止の判断を優先することが推奨されています。救命胴衣の着用は必須で、国土交通省や海上保安庁が周知している通り、安全基準を満たしたものを使用することが重要です(出典:海上保安庁 海の安全情報)。
6月の泳がせ釣りとフカセ釣りの釣り方

6月は泳がせ釣りとフカセ釣りが特に効果を発揮しやすい時期です。泳がせ釣りはアジやイワシなどの小魚を活き餌として用い、フィッシュイーター(肉食魚)を狙う方法で、青物やヒラメ、マゴチなどがターゲットになります。
一方、フカセ釣りはコマセ(撒き餌)を用いて魚を浮かせ、同調させた仕掛けで食わせる手法で、主にチヌやグレが対象となります。
泳がせ釣り(堤防・磯)
活餌を自然に泳がせるため、ウキ泳がせ仕掛けや胴付き仕掛けを用います。基本は潮下へ自然に流し、魚に違和感を与えないことが重要です。ドラグはやや緩めに設定し、魚が違和感なく餌を咥える時間を確保するのがポイントです。
フカセ釣り(チヌ・グレ)
フカセ釣りでは潮の当たる面にコマセと仕掛けを同調させることが最重要です。コマセの沈降速度と仕掛けの馴染みを一致させ、自然に漂わせることで魚に食わせやすくします。濁りが強いときは視認性を確保するため、浮力の強い大きめのウキを使用するのも効果的です。
資源保護の観点から泳がせ釣りやフカセ釣りで使用する餌や魚種には、地域によって採捕制限やサイズ規制が設けられている場合があります。水産行政や自治体が発表する最新の指針を確認し、遵守することが求められます。
6月の愛知・千葉・関東の釣り傾向

6月は愛知や千葉、関東エリアでの釣りにおいて多彩な魚種が狙える季節とされています。伊勢湾や三河湾を抱える愛知では、河川からの濁りが入りやすい環境のため、チヌやキス、マゴチといった底物系が特に活発になります。
湾奥ではシーバスが河川流入部に集まりやすく、ルアーでの攻略が有効です。千葉では外房の黒潮影響を受けたエリアでイサキや回遊魚が好調であり、内房から東京湾側にかけてはアジやチヌ、シーバスが多くの釣り人に狙われています。
関東広域では相模湾や東京湾のシロギス釣りが例年人気を集め、房総半島の外洋エリアでは小型青物やイサキの釣果も安定している傾向が報告されています。
地域ごとの釣果傾向は、潮流の向きや気象条件に大きく左右されます。
例えば、愛知の湾内は梅雨時の降雨で濁りが強くなるため、視認性の高いルアーカラーが効果的です。千葉外房のように外洋に面した地域では、黒潮の接近に伴い水温が上昇し、イサキや小型青物の群れが接岸するケースがあります。
関東全体では、河川や汽水域でのシーバスやチヌの実績が高く、雨後の濁りや増水が好条件になることも知られています。
梅雨釣りの総まとめと次の一
- 出発前は気象警報と雷予測を確認し危険回避
- 潮位差と干満時刻を把握して時合いを読む
- 濁り時は波動とシルエットで存在感を出す
- 夜は常夜灯の明暗と流れの当たる面を狙う
- ルアー色は水色と光量で高対比を選択する
- 堤防は安全最優先で高波や滑りを避ける
- 船釣りは風浪と指示棚厳守で手返しを上げる
- 泳がせは送り込み重視で違和感を与えない
- フカセは同調と馴染み速度の管理が重要
- 地域傾向は公的データと現地情報で補強
- 雨具は防水透湿と撥水回復で快適性維持
- 常時ライフジャケットで落水リスクを抑制
- 退避基準を数値化し迷いなく中止判断する
- 釣り 梅雨の特性を学び釣行計画に反映する
- 次回は潮汐と天候から最適地を先に選ぶ
以上の要点を押さえることで、梅雨時期の釣行は安全かつ効率的に楽しむことができます。
気象や潮汐などの自然条件を理解し、装備や戦略を柔軟に調整することが、6月の釣りにおいて安定した釣果と安全確保につながるとされています。
公的機関が発表する一次情報を基準に、現地の声を加味しながら行動することが、次の一手を導く最大の武器になるでしょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
ほかにもおすすめの記事を紹介しているので、ぜひあわせてチェックしてみてくださいね!
👇👇👇





